

お知らせ
NewsZEH住宅にデメリットはある?知っておきたい注意点を紹介

ZEH(ゼッチ)住宅は、エネルギー消費を抑えつつ快適な住まいを実現できるとして、近年注目を集めています。
断熱性や省エネ性能に優れ、長期的には光熱費の削減や環境への配慮につながるなど、メリットの多い住宅スタイルです。
しかし、導入コストや間取りの制約など、実際に建てる前に知っておくべきデメリットもあります。
この記事では、ZEH住宅の特徴やメリット・デメリットなど、後悔しないために押さえておきたいポイントを紹介します。
ZEH住宅とは
ZEH(ゼッチ)とは「net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略で、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にすることを目指した住宅を指します。

具体的には、住宅の断熱性能を高めてエネルギー消費を抑えると同時に、太陽光発電などでエネルギーを創出し、消費と創出のバランスを取る仕組みです。
(出典:資源エネルギー庁「ZEHの定義(改訂版)」)
ZEHの普及は国の重要政策の一つであり、一定の基準を満たした住宅には補助金制度が設けられています。
経済産業省と環境省による「ZEH補助事業」では、ZEH住宅1戸あたり最大55万円の補助金が交付されるほか、より高性能な住宅に対して補助額が上乗せされる「次世代ZEH+」という制度も活用可能です。
ZEH住宅には、主に以下の3つの特徴があります。
断熱
ZEH住宅では、建物全体に高断熱・高気密な素材を使用することで、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を維持しやすくなります。
これは外気の影響を受けにくくし、冷暖房効率を高めるためです。
ZEHとして認定されるには、「断熱等性能等級5(断熱等級5)」以上の基準をクリアする必要があります。
(出典:国土交通省「省エネルギー性能に係る上位等級の創設」)
断熱等級5とは、2022年に新設された等級であり、従来の省エネ基準(等級4)を上回る断熱性能が求められます。
等級は地域区分に応じたUA値(外皮平均熱貫流率)で基準に認定されており、愛知県や岐阜県が該当する「6地域」では、UA値0.60W/(㎡・K)以下が基準となっています。
このような基準を満たすことで、冷暖房の使用を抑えつつ快適な室内温度を維持できるのです。
省エネ
ZEH住宅では、空調・給湯・照明・換気といった生活インフラにおいて、省エネ性能の高い設備が採用されています。
これにより、家庭全体のエネルギー消費量を大幅に削減できます。
また、多くのZEH住宅ではHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)が導入されており、エネルギー使用量の見える化が可能です。
どの設備がどれだけエネルギーを使っているかを把握できるため、日常的な省エネ意識の向上にもつながります。
創エネ
ZEHの大きな特徴のひとつが「創エネ」、つまりエネルギーを自ら生み出す仕組みです。
主に太陽光発電システムが採用され、自宅で発電した電力を自家消費することで、電力会社から購入する電力量を減らすことができます。
また、発電量が消費量を上回った際は、余剰電力を蓄電池に貯めて夜間に使ったり、売電することも可能です。
ZEH住宅のメリット

ZEH住宅には、省エネ性や快適性だけでなく、防災や経済面でも多くのメリットがあります。
光熱費を削減できる
ZEH住宅は、高断熱・高気密の設計に加えて、省エネ機器や太陽光発電システムなどを導入することで、家庭で消費するエネルギーを最小限に抑えられます。
昼間に発電した電気を家庭で使用し、余剰分は蓄電または売電することで、電力会社からの購入電力を大幅に減らせるでしょう。
これにより、毎月の電気代やガス代などの光熱費が抑えられ、長期的に見れば大きな節約効果が期待できます。
災害時も電力を確保しやすい
太陽光発電や蓄電池を備えたZEH住宅なら、災害などによる停電時にも、冷蔵庫やスマートフォンの充電、照明などの最低限の電力を確保しやすく、安心感につながります。
停電時にも生活機能を維持できる点は、防災意識の高い方にとって大きな安心材料です。
特に地震や台風の多い日本では、非常時の電力自給は重要な要素といえるでしょう。
補助金が受けられる
ZEH住宅は、国の普及促進政策の対象となっており、所定の条件を満たすことで補助金を受けられます。
2025年度の例では、基本補助金として1戸あたり55万円が支給されるほか、蓄電池などの追加設備に応じた加算措置もあります。
これにより、初期費用の負担を軽減しながら、高性能な住宅を建てられるのがメリットです。
1年中快適な室内環境
優れた断熱性と気密性を備えたZEH住宅では、外気の影響を受けにくく、室温が安定しやすいため、夏の暑さや冬の寒さを感じにくい快適な住環境が得られます。
また、急激な温度差によるヒートショックなどの健康リスクも軽減でき、家族の健康維持にも貢献するでしょう。
資産価値の上昇が期待できる
ZEH基準を満たす住宅は、省エネ性能や断熱性能といった性能値が明確で、環境配慮型の住宅として市場から高く評価されやすい傾向にあります。
そのため、将来的な資産価値の下落リスクが低く、中古住宅市場においても優位性を保てる点はメリットの一つです。
ZEH住宅のデメリット
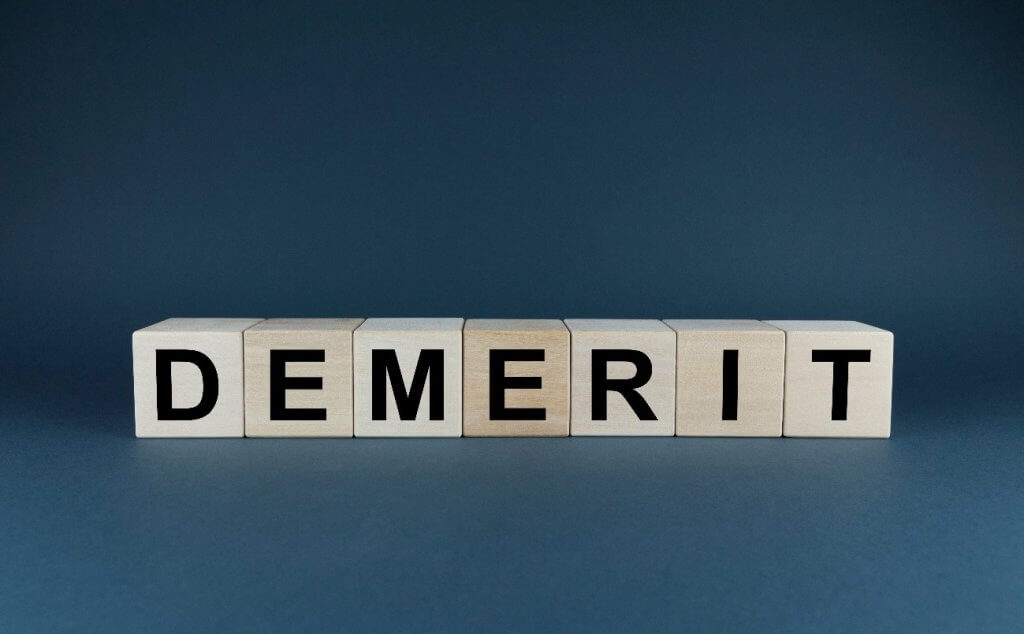
ZEH住宅は省エネ性や快適性に優れていますが、導入時や居住後に注意すべき点もあります。
続いては、後悔を防ぐために知っておきたい主なデメリットを紹介します。
建築コストが高くなる
ZEH住宅は、高性能な断熱材や高効率設備(太陽光発電、HEMS、蓄電池など)の導入が前提となるため、一般的な住宅に比べて初期費用が高くなる傾向があります。
初期費用は200〜300万円ほど上乗せされるケースもあり、補助金を活用しても割高になるため、予算に余裕を持って計画を立てることが大切です。
間取りやデザインが制約されやすい
ZEH住宅では、太陽光パネルを効率的に設置するために屋根の形状や勾配に制限が出る場合があります。
また、高断熱仕様にすることで壁が厚くなり、部屋の面積に影響したり、窓の大きさや配置にも配慮が必要になるでしょう。
その結果、デザインや間取りにおいて自由度が下がり、「理想の外観や間取りを実現しにくい」と感じるケースもあるようです。
メンテナンスコストがかかる
太陽光発電や蓄電池、エコキュートなどの高性能設備は定期的なメンテナンスが必要です。
5〜10年に一度の点検で数万円の費用がかかるほか、15〜20年後にはパワーコンディショナや蓄電池などの交換に数十万円が必要となる場合もあります。
長期的な維持管理費を見越して、ライフプランを立てておくことが重要です。
地域や敷地条件によっては非対応
ZEH住宅には、十分な日照時間や屋根面積が求められるため、隣接する建物の影や狭小地、北向きの土地などでは計画が難しいことがあります。
また、災害危険区域や土砂災害特別警戒区域などの一部地域では、補助金の対象外となる場合もあるため、計画段階での事前確認が重要です。
ZEH補助金を申請する際の注意点
ZEH補助金は国の予算に基づいて交付されており、予算枠に達し次第、年度の途中でも受付が終了することがあります。
そのため、補助金を確実に活用したい場合は、早めの情報収集と申請準備が重要です。
申請にはいくつかの条件があります。
まず、対象となる住宅の設計・建築を担当する事業者が、「ZEHビルダー」または「ZEHプランナー」として経済産業省に登録されていることが必須です。
注文住宅の施工を依頼する工務店が、ZEHビルダーとして登録されているかどうかは、事前に公式サイトで確認しておきましょう。
また、ZEH補助金は毎年内容が見直されるため、補助金の金額や要件、申請スケジュールも年度によって異なります。
申請にあたっては、SII(環境共創イニシアチブ)や経済産業省の公式サイトで最新の情報を必ずチェックし、手続きに必要な書類や期限を見落とさないよう注意が必要です。
愛知県・岐阜県のZEH住宅は工務店「善匠」(ZEHビルダー)にご相談ください

ZEH住宅には、光熱費の削減や快適な室内環境の維持、災害時の電力確保、資産価値の維持向上といった多数のメリットがあります。
その一方で、建築コストや設計の制限、設備の維持管理など、事前に理解しておくべきデメリットや注意点もあるため、慎重に検討することが大切です。
愛知県・岐阜県でZEH住宅の建築をご検討中の方は、ZEHビルダーに認定されている工務店「善匠」にぜひご相談ください。
ZEH基準を満たす住宅設計はもちろん、補助金制度の活用方法やライフプランに合わせた資金計画についても、経験豊富なスタッフが丁寧にご案内いたします。
善匠では、各地のモデルハウスでZEH住宅の快適性を体感できる見学も随時受付中です。
Webからの来場予約も可能ですので、ぜひお気軽にご来場ください。
#名古屋工務店 #愛知工務店 #岐阜工務店 #工務店
#注文住宅 #注文住宅愛知



